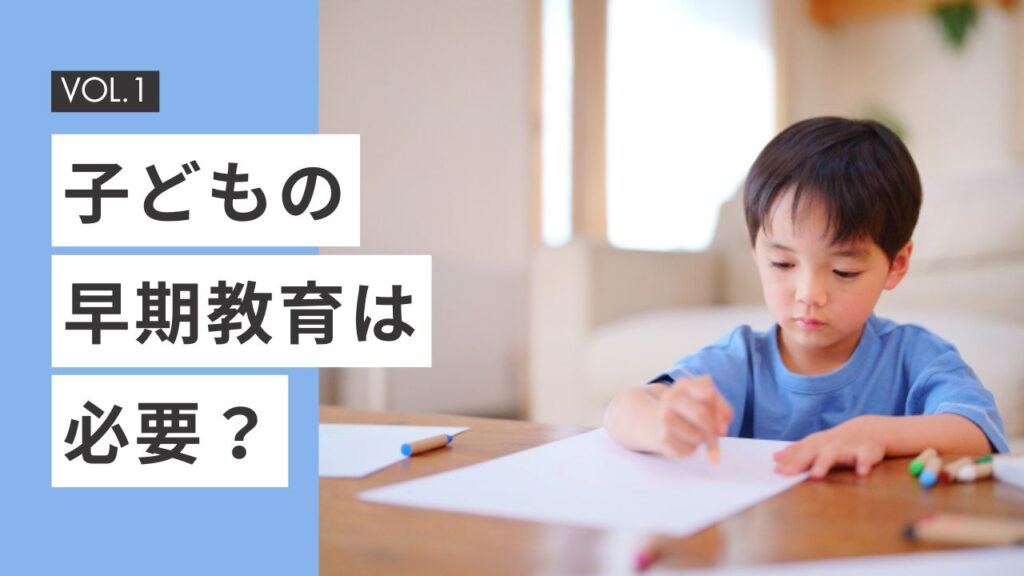
こうした議論をする際にまず気をつけなくてはならないのは、言葉の定義です。
研究者の論文はまず扱う言葉の定義からはじめるのですが、その論文の結論が雑誌やWEB記事などで世に出回る時には、そもそもの言葉の定義が忘れられたまま、早期教育の有効性は無いだとか、早期教育は人生に影響を与えるだとか語られます。
購買数やページビューが稼げるなら、ライターさんにとってそんなことはどうでも良いのかもしれませんが、それを読んで混乱させられる方はたまったものではありませんよね。
また、そうした不確実な情報に親御さんが右往左往させられることが、お子さんへの教育にとって良いものとはとても思えません。
というわけで、ここではまず、言葉の定義について考え、それから、その必要性について、そして、本当に気をつけるべきことについて、考えていきたいと思います。
早期教育という時の「教育」とは何を指しているのでしょうか。
それはおそらく、親が積極的に子どもに与える何らかの知的訓練を指しているのでしょう。
そして、それが公的教育よりも先になされることを「早期」教育と呼んでいるのでしょう。
さて、こうして定義してみると、おかしなことに気づくはずです。
私たちは普通、何らかの形でその意味での早期教育をしてしまっているからです。
絵本を読んであげること、散歩に連れていって色々なものを見せてあげること、話しかけてあげること、これらはすべて知的訓練です。
デューイという今なお教育界に影響を与えつづけている教育思想家は、教育を養育と連続したものとして捉えます。
養い育むことと、教え育てることは、本来、連続しているというのです。
こうしたデューイの観点に立てば、早期教育は必要に決まっていますし、その気がなくても「してしまっている」ものだと気づくはずです。
ここまでお話ししたところで、「いや、私の聞きたい早期教育というのは、それではありません」とおっしゃられる方がいらっしゃるかもしれません。
そうした方のいう早期教育というのは、おそらく、他の機関に任せて行う「専門的な(?)」知的訓練のことだろうと思います。
さて、実は、論題のもう一つの言葉について吟味しなければならなかったのですが、ここまで敢えてそれに気づかないふりをしてまいりました。
それは、「必要」という言葉です。
「必要」という語は、ふつう、「〇〇のために」という対象を必要とする語です。
早期教育が必要かどうかを知りたい方々の心の内には、実は、この「〇〇」があるはずなのです。
例えば、良い中高一貫校に受かるために、とか、良い大学に進学するために、とか、あるいはまた、他のお母さんにマウントを取るために、などなど。
それが本当にお子さんのために必要なのかはさておき、専門機関による早期教育が「必要」だと言った場合、この〇〇に入るのは、なんでしょうか。
私たちの考えでは、早期の教育が必要なのは、「早期のテストに受かるために」だけです。
各ご家庭いろんな事情がおありでしょうから、その「必要」を否定するつもりは毛頭ありませんが、それでも、ほとんどのご家庭にとって、そうした早期教育が必要であるとは私たちには思えません。
いや、むしろ、長い目で見た教育においては大失敗を引き起こすのではないかとさえ考えているのです。
デューイにまた登場いただきましょう。
デューイによれば、教育の本質とは、価値観の伝達です。
家庭や地域などの共同体において大人と接するなかで、子どもたちは価値観を形成していきます。
家庭の大切にする価値観、地域の大切にする価値観が、子どもに伝達されていくのです。
そうした価値観をもとに、子どもは自発的に、いろんな選択をし、人生を切り拓いていくわけです。子どもはロボットではありません。自主的に考え、選択し、努力し、人生の道を切り拓いていくのです。
その際、子どもたちを助けてくれる「正しい価値観」とはどのようなものでしょうか。
それは、他人よりも努力し、丁寧に学び、他者に気を配り、信頼され、難題に直面しても諦めず、仲間に頼りながら、創意工夫できるような人物につながる価値観ではないでしょうか。
有能で信頼される人物、それは「損得勘定」とは全く逆の価値観を持っているのではないでしょうか。
ここで考えてみていただきたいのです。
皆さんが早期教育が必要かもしれないと考えている時の、その心の内に隠れている「〇〇のために」の「〇〇」が、果たして損得勘定に根ざしていないかどうかです。
もしそうならば、その価値観がお子さんに伝わっていくことでしょう。
それは、お子さんが逞しく生きていくうえでは躓きの石となるかもしれません。
何が大切かをもう一度静かに考えてみていただければと思います。